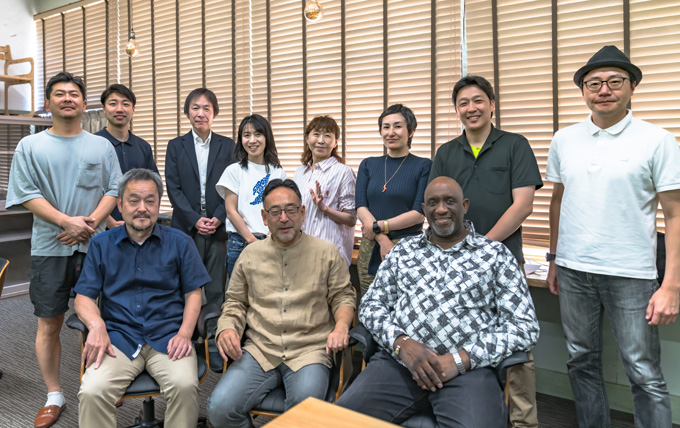「佐渡から考える島国ニッポンの未来」
学校蔵の特別授業2024
DAY:2024.6.15 現場レポート たまきゆきこ(学校蔵雑芸員)

ついに10回目を迎えた・佐渡旧三川小学校「学校蔵」での特別授業。
今年は、藻谷浩介さんと、これまで講師として、鋭くかつ深く、けれども優しく温かなお話をしてくださってきたお二人、ウスビ・サコさん、玄田有史さん、とが、課題提起と意見交換をし、参加している皆さんとともに、佐渡から未来を考えていく、という何とも贅沢な企画。
自然・文化・歴史に多様性があり、“日本の縮図”と言われている「佐渡」。
 同時に、日本の課題が詰まっているという意味でも“日本の縮図”であり、課題先進地ともいえ、これは、捉え方を変えれば課題解決機会がたくさん詰まっている“課題解決先進地”になる。この島で何かのヒントが得られれば、大きな島国・ニッポンの未来に役立つかもしれない… 平島校長、留美子学級委員長が考え続けてきたこのテーマの、10回一区切りともいえる集大成の時間となりました。そして、ニッポンの未来、としながらも“佐渡の未来”をみんなで考えていきたい、というお二人の佐渡という地への想いの深さを改めて感じた特別授業でもありました。
同時に、日本の課題が詰まっているという意味でも“日本の縮図”であり、課題先進地ともいえ、これは、捉え方を変えれば課題解決機会がたくさん詰まっている“課題解決先進地”になる。この島で何かのヒントが得られれば、大きな島国・ニッポンの未来に役立つかもしれない… 平島校長、留美子学級委員長が考え続けてきたこのテーマの、10回一区切りともいえる集大成の時間となりました。そして、ニッポンの未来、としながらも“佐渡の未来”をみんなで考えていきたい、というお二人の佐渡という地への想いの深さを改めて感じた特別授業でもありました。
講師お三方が、テーマごとにお二人ずつ意見を交わし合った今回。示唆に富んだお話、だけれども、笑いあり、鋭い指摘あり、みんなでクスクス、ケラケラ〜っとしているうちに、課題の真髄にすっと入っていってしまうような…、講師お三方の巧みな理論構成、そしてわかりやすい言葉でありながらも、お話の余韻が深く残って、あのお話ってもしかしたらこんなことを指摘していたんだ、とあとになって気づくような… この特別授業ならではの議論でした。
動画配信もされている特別授業ですので、そちらをご覧いただくことで当日の様子も、講師お三方のお考えもよくわかるのですが… 自分なりに講師の方々のお話を咀嚼しようとしてみた(今回も、やっぱり相当に消化不良ですが)メモです。

■1限目 限界集落の限界 藻谷浩介さん×玄田有史さん
 限界集落ってどういうこと? いつから言われ始めた? ヤクショで使ってるの? 新聞記事で書かれている? 「限界集落」や「消滅自治体」といった言葉は、最初に用いた方が意図した想いとは異なる解釈が加わり拡がっていったもの。では、なんとなく皆が使っている「限界集落」の定義を知っている人は… と、数字から正しく定義を把握するという藻谷さんからの質問はいつも、改めて日頃、“なんとなく、だいたい…”の情報から物事を捉えてしまっているということについて省みる機会でもあります。
限界集落ってどういうこと? いつから言われ始めた? ヤクショで使ってるの? 新聞記事で書かれている? 「限界集落」や「消滅自治体」といった言葉は、最初に用いた方が意図した想いとは異なる解釈が加わり拡がっていったもの。では、なんとなく皆が使っている「限界集落」の定義を知っている人は… と、数字から正しく定義を把握するという藻谷さんからの質問はいつも、改めて日頃、“なんとなく、だいたい…”の情報から物事を捉えてしまっているということについて省みる機会でもあります。
65歳以上は高齢者、住民の半数が65歳以上だと何が「限界」なのか?
人口減少は、日本の多くの地域が直面する課題ですが、人口減少のどこをみていくのか。2023年総人口の2018年比で人口増加がみられる、東京都(+1%)、大阪市(+1%)、さいたま市(+4%)に対し、新潟市(▲3%)、佐渡市(▲10%)。このうち、15〜44歳人口(若者人口)をみると、新潟市(▲11%)、佐渡市(▲16%)のみならず、東京都(▲4%)、大阪市(▲1%)、さいたま市(▲1%)。この理由は? の問いに、参加者から正解が。それは急速に進んでいる少子化。若者は希少な存在、希少価値だ… 藻谷さん、玄田さんのかけあいに会場からは笑い声があがりましたが、かなりに多方面に影響が顕れていくことになる深刻な課題です。
さらに、2023年65歳以上人口の2018年比・高齢化率をみていくと、東京都(23%)、大阪市(25%)、さいたま市(23%)、新潟市(30%)、佐渡市(42%)。これを75歳以上の増加率でみると、東京都(12%)、大阪市(9%)、さいたま市(20%)、新潟市(10%)、佐渡市(▲8%)。
今後、高齢者対策が必須となるのは都市部であって、さらに社会保障サービスのニーズは増嵩し、施設も人的資本も足りなくなる。介護福祉人材確保が一層深刻となっていく大都市圏に地方から人材流出が進む可能性も含め、社会保障、福祉制度と政策の在り方もよく議論がなされていかなければならないし、描かれる未来についてを、次世代が考え対処すべき課題とせずに、普遍性を考える必要があるということ。そして、そのためには曖昧な概念ではなく、事象を正しいデータから読み解く力を私たちが身に着けている必要がある、ということ。
 藻谷さんは、今までもずっと言ってきたと前置きしつつ、起きている事実を客観的に把握することがいかに大切か、現実の数字を把握した上での政策・対策を講じようとしているのか、と。2050年の日本はどうなっているのか… 地方の若者が減り過ぎると都会への流入も減り“都会も消滅に向かう”のか、それとも、過疎地から先に高齢者が増えなくなり、若者を受け入れる“一部の過疎地は子どもが再び増え、都会より先に再生に向かう”のか…
藻谷さんは、今までもずっと言ってきたと前置きしつつ、起きている事実を客観的に把握することがいかに大切か、現実の数字を把握した上での政策・対策を講じようとしているのか、と。2050年の日本はどうなっているのか… 地方の若者が減り過ぎると都会への流入も減り“都会も消滅に向かう”のか、それとも、過疎地から先に高齢者が増えなくなり、若者を受け入れる“一部の過疎地は子どもが再び増え、都会より先に再生に向かう”のか…
限界集落が限界を迎えることから生じる課題はその地域ではなく、より多くの人口を抱える地域、都市の限界を顕わにするものであって、課題となっている事象の正体を正しいデータから読み解きながら、再生に向かうことができる地域を創っていくこと、を考える。限界集落の限界を見極めた先に、希望を見出せるのかどうかのヒントは、私たち自身のなかにある。
そして限界の限界を目指すのには、コネタがある地域でありたい、と玄田さんからKNT理論についてのボールも飛んできた、一限目でした。
■関係人口の正体 ウスビ・サコさん×玄田有史さん
今日はダイアログがしたい。けれど最初に、少しデータ的なことから説明したい、とウスビ・サコさんの出身地、西アフリカのマリ共和国のデータから始まった2限目。公用語はフランス語だけれども、23以上の民族の言語があって、識字率(公用語)は3割ほど。それでも選挙のマニフェストも役所などで必要な書類も公用語。この状況に対して近年、フランス語を捨てましょうという運動も起きてきている、と。マリ共和国のことについて聞くのは多分初めて、という方もきっと多くいらして… みんな興味深々。
 思考の言語と日常の言語が違い、学校で用いられる小説などではフランスでのことが描かれるというイリュージョンのような状況。外から国を統治されるとういうことは、こういうことだと皆さんには覚えておいて欲しい、とサコさん。そして、多言語、多民族国家であるマリは共通の言語が無いゆえに、文字による意識共有が難しい、だから話し合いが必要。国における最も古い憲法は口承によって伝えられ世界無形文化遺産リストにも登録されている。(※マンデン憲章)
思考の言語と日常の言語が違い、学校で用いられる小説などではフランスでのことが描かれるというイリュージョンのような状況。外から国を統治されるとういうことは、こういうことだと皆さんには覚えておいて欲しい、とサコさん。そして、多言語、多民族国家であるマリは共通の言語が無いゆえに、文字による意識共有が難しい、だから話し合いが必要。国における最も古い憲法は口承によって伝えられ世界無形文化遺産リストにも登録されている。(※マンデン憲章)
佐渡も、みなが集まって話し合って共通の憲法を創っていくと良いのではないか、と。そして、マリではその口承は音楽によって語り部たちが伝えてきたとも。第8回特別授業にサコさんが来島された際、学校蔵に向かう途中で偶然出会ったのが、春の例大祭にあわせ門付けをしていた鬼太鼓。遠くから移動してくるトントコトンという太鼓の音と若衆の掛け声と。車を降りて、鬼太鼓の面々にすぐに声をかけていらしたサコさんの姿を思い出しながら、佐渡ならもしかしたら出来るのかも…と、想いました。他者とのコミュニケーションを視覚からだけではなく、私たちが持っている五感全体を使って行ってきたということ、を。
続いてサコさんはマリの家族、中庭のある家についてのお話を。実際の図面と各部屋に誰が何人で暮らしているか等、学生と実際に調査した結果を示しながら、こうしたマリの家の構造は「近代建築としてはあり得ない」と続けます。日本の住宅は狭いというが、マリの家における一人当たりでみた空間の占有率は更に狭く、人々は、区切られているようにみえる各部屋と中庭とを、日々の生活における目的に応じ移動しながら暮らしていく。各部屋に住まう家族同士がネゴシエーションしながら、空間を使っていく。共生している、ということはお互いの行動を観察し合えるということ、これが重要だ、と。反対に、プライベートを重視し、個の空間を確保し、均質空間のなかで部屋の外にある危険から身を守るため壁を造り、音や風の流れも、他者からの過干渉も遮断できるところ、が家であるとしてきた近現代の私たちの生活… あれ、でも、例えば江戸期の風俗画に描かれている長屋暮らしって…?
実際の数字から真実を把握する力についてのこと、と同じく、実際に他の
国で今も行われている生活の様相、空間の使われ方を、そのことによって何が今の我々と異なっているのかを客観的に可視化していくこと、で明らかになっていく、課題の根幹。
サコさんはさらに、言語と言葉とは違う、マリではこの二つの概念を分けていると続けます。“言葉”とは、文字を介さず他者に直接伝える、「音とイメージとがつながっている」もの。一方、「文字を介することで構造化されている」のが“言語”。学校でフランス語という言語を学び、毎日の生活でのコミュニケーションは言葉によって紡がれていく、のがマリだと。サコさんがお話の冒頭で面白おかしく話された、マリでの入国審査の際の長話、冗談の方が多いようなやりとりのことも、あぁそうなんだ、と。相手のことを知るために、相互のことを覚知しあうために“言葉”が必要なんだと。構造化され、ルールに則って話される“言語”で使われる我々の感覚は視覚が主であって、“言葉”には、声の調子、時にはからだの動きなど、視覚以外の感覚も使いながら私たちは相手の言っていることを理解しようとするチカラをもっているのだから。そして今、私たちはそれらを使えているのか…
 サコさんのお話を受け、玄田さんはこれ読める?と「巫山戯」と黒板に。
ふざける、ということは“言葉”を使うということでもあるし、マリの家にある中庭と同じ役割を果たしてきたであろう空間としての広場、には、そこで遊ぶ子供たちを見守っている他者がいたし、広場があるところで社会を変える何かが起きてきたよね、と。それを受けてサコさんは、日本の今の広場、は、管理する人とそこを使う人とが同じではないこと、の違和感について話を続けられました。使わない人がルールを決めていること、それは「コモンズ」ではない、と。サコさんの言われる「コモンズ」とは、日本における近代以降の「入会地(入会する権利を持った者たちが所有・管理する地)」とはおそらくは異なっていて、誰の所有にも属さない放牧地のような共有地のことであって、いつ草を刈るのか、或いは何時から何時までを家畜たちの放牧地とできるのか、餌となる草の管理を、利用する者たち、当事者同士が自分たちで決めている場所のこと、だと。日本はいつから、広場を公が管理する場所にしていったのか…
サコさんのお話を受け、玄田さんはこれ読める?と「巫山戯」と黒板に。
ふざける、ということは“言葉”を使うということでもあるし、マリの家にある中庭と同じ役割を果たしてきたであろう空間としての広場、には、そこで遊ぶ子供たちを見守っている他者がいたし、広場があるところで社会を変える何かが起きてきたよね、と。それを受けてサコさんは、日本の今の広場、は、管理する人とそこを使う人とが同じではないこと、の違和感について話を続けられました。使わない人がルールを決めていること、それは「コモンズ」ではない、と。サコさんの言われる「コモンズ」とは、日本における近代以降の「入会地(入会する権利を持った者たちが所有・管理する地)」とはおそらくは異なっていて、誰の所有にも属さない放牧地のような共有地のことであって、いつ草を刈るのか、或いは何時から何時までを家畜たちの放牧地とできるのか、餌となる草の管理を、利用する者たち、当事者同士が自分たちで決めている場所のこと、だと。日本はいつから、広場を公が管理する場所にしていったのか…
そしてサコさんは、マリの人口が増えている理由として、子供はみんなで育てるものだから、と。中庭空間、広場、コモンズ… 厚く強固な壁によって守られた部屋の中で家族のみで子どもを育てること、と。今回の授業では、時間が足りなくてダイアログまでいけなかった、このことを、次回もっと、言葉で話し合えたらいいなぁ…。
2限目のテーマは「関係人口」についてでしたが、サコさんは関わりというのは、どこに住んでいるかではなく、関わり合うということ。でありながら、日本では「関わりあうこと」が、難しいのではないかと。その一例として〇〇反対!という看板が家の扉や町のあちこちに立っていた光景を紹介されました。“かかわりあう”ということってどういうことなんだろう… サコさんの問いかけに玄田さんは、Well-beingではなくWell-becomingということなのではないか、と受けます。Being=〇〇になる、ということはしっくりこないが、〇〇という“変化を変化として受けとめながら”毎日を大切に生きていく、ということ。さらに言うと、“Co-becoming”誰かとともに変化を受けとめていけるといいのではないか、と。そして“Co-becoming”と同じ意味を有する漢字一文字は“仁”である、と。漢字の成り立ちのとおり、人はひとりではあらず、が我々にはしっくりくるのではないか、「関係人口を「関係仁口とするとどうだろうか、と。
 これがオチ、だったんだよと笑いながら締め括られましたが、私たちの日常は不条理なことの方が実際には多くありそうした不条理を自身が飲み込み納得させていく過程にあっても、なおかつ私たちが希望を持てるということ、とは、ひとりにはあらず、そして、言葉によって互いを知ろうとすること、なのではないかと…
これがオチ、だったんだよと笑いながら締め括られましたが、私たちの日常は不条理なことの方が実際には多くありそうした不条理を自身が飲み込み納得させていく過程にあっても、なおかつ私たちが希望を持てるということ、とは、ひとりにはあらず、そして、言葉によって互いを知ろうとすること、なのではないかと…
一人では成り立たない。そして二人以上となるためには場所が必要で、そのための関係を作っていかなければならない。この“関係”をどう創っていくのか、について、サコさんはマリでは“借りをつくる”ということだと。そしてそれはできるだけ長い期間、である方が良い。迷惑をいかにかけ合うことができるか、だと。省みて、今の建築は「いかにして他者に迷惑をかけないような空間をつくること」に傾注していると。プライバシーを尊重し、相手のことは聞こえない、遮断し孤立化させてきた近代空間に対し、佐渡にはまだ可能性が残っているでしょう、と。迷惑をかけあえる人々の集団が「関係人口仁口」だと。玄田さんは、迷惑をかけ合える関係は、損得勘定を超えて波動を共有しあえるということ、と。サコさんは、波動、響き合えるという言葉は、レゾナンス Resonance(共鳴、共振)だと話されました。マリの音楽はまさにこれだよね、と藻谷さんからも。
アフリカやアジア、古いヨーロッパの民俗音楽も含め、このResonanceが音楽の重要な要素でした。太鼓の裏面に糸を張ることで、叩かれる面の動きに糸の揺れが共振し振幅が増大する。雑音のようだと削られてきたこうした音、倍音の世界は、一つのものからは生まれないので。
Hope is Wish for Something to Come True by Action. ― 『希望学』についてを高校生たちに語る際に玄田さんが使われているフレーズですが、きっとここに with Others を加えよう、ということなのではないかな…
波動を無理に合わせようとするのではなく、合わなくてもよい。このことが、3限目「島国根性のススメ」におけるハイコンテクストか、ローコンテクストか、の議論ともつながっていく2限目となりました。
■3限目「島国根性のススメ」 藻谷浩介さん×ウスビ・サコさん
長々と書き過ぎてしまう雑芸員の悪い癖… 3限目のお二人のお話はぜひに、動画でご確認ください(*^^*)
(限定公開) https://youtu.be/c1ZEBtTtJYk?si=3cl8XY4shgMKgMqb
■4限目 のスピンオフ(雑芸員の雑記です)
前回、第9回目の特別授業、養老孟司さんと藻谷浩介さんのお話のなかで、藻谷さんは、「日本の教育は人工知能育成型だ
と。何が一番常識的かをネットで検索しながら、多くの人が言っているのはこういったこと、そしてそこに少し反論の意見を同じく検索し盛り込みながら、最大公約数的な、多くの人が書いていそうな文章を組み立てていく。常識的なことを学び「暗記する
ことと、反対意見を言いつつも「同調していける力
を身につけていく。「常識暗記力+集団同調力」これが日本の教育における「鍛えるべきこと」になっていると指摘されました。
養老さんは、どうやって必要なものを調達し、それを必要充分として皆でやっていけるか。日本が最先端の国か後進国か、は結局のところ、物差しの当て方でしかないことであって、「自然とは、自ずから然り。ひとりで(自ずから)に、よろしい(然り)、ひとりでにできればよい
と。佐渡は、それができる場所、でしょうね、と。そう締め括られました。
『唯脳論』で養老さんは、都市社会を人間の意識が作ったという意味で「脳化社会」と呼び、その利便性の中で暮らすことは、生き物としての感覚を衰えさせると警鐘を鳴らしておられます。生身の人間の自然性は、意識ではコントロールできない。故に、高度に発達する都市社会への懐疑を伴う、と。
今回、迷惑をかけ合える、共振しあう関係性を創る場、についてのお話を伺いながら改めて、かけがえのない関係性をつくっていく、関係性をつなげていく、ということは、無駄を省きシステム化できないことを除いてきた現代社会が、そうした無駄をノイズと呼び、子どもの遊ぶ声さえノイズだと意識する人が増え、かけがえのない命に対する畏れのような感覚を鈍くさせているのではないか、とのお話とつながっている、と想いました。
 最前列で今回も特別授業を聞いてくれた、島の高校生の皆さん。皆さんが今暮らしている場で、何が起きているのか、先達が見ていた先にある世界は、今どうなっているのか。そして、あなたは、私は、今日の実感をどう明日へとつないでいくのか。
最前列で今回も特別授業を聞いてくれた、島の高校生の皆さん。皆さんが今暮らしている場で、何が起きているのか、先達が見ていた先にある世界は、今どうなっているのか。そして、あなたは、私は、今日の実感をどう明日へとつないでいくのか。
いつも、多くの示唆と次への課題についての投げかけがある、この特別授業。
私自身は、授業のあと、見聞したいくつかの講演、インタビュー等から、特別講師のお三方が話され特に印象に残ったキーワードと通奏するのではないかと考えたことを、最後に3つ記させていただきます。
ひとつは世界的な文化人類学者、ティム・インゴルド氏のお話から。
― 自然を超越し近代文明を築いていった人類が未来へと進歩していくという一方向的な見方は、資源枯渇の問題を背景に植民地主義や環境破壊などの課題を生んできましたが、だからといって進歩を止めて停滞することを目指せばよいということではなく、過去と未来、双方を同じように見つめながら自己や世界を作っていくことが重要であること。そして、「大事なことは、対象と同じ方向を向くこと」だと。
Cultureとは自然をコントロールして作るものとみなすのではなく、「守る」とか「手入れをする」という本来の語源に戻り、対象を大切にするということであって、教える側、教わる側、という今の「アカデミック」な教育の姿を再構成しようとすることを実践できる場を創ること、であると。
森の木が船として海へと漕ぎ出すように、ある一つの存在はライフサイ クルの中で変化していき、変化の中でそれ自体が再生されていく。それぞれの瞬間の中に、永続的な生命の動きがあり、すべての時間が内包されていると考えている。生きるための知恵がたくさん残っていること、自分自身も学んで変わっていくことが大切だと思えること。
人類学とは、データや被験者を解析して結論を付ける研究、人々『につ いて』研究するのではなく、人々『とともに』学んでいく姿勢であって、ともに生きるためには「混ざり合えば混ざり合うほど良い。色々な種の絡まり合い、複雑なものを複雑なまま理解することが大事であって、違いがあるから、一緒になれる。全く同じ経験しか持たない人たちの中に会話は生じない。(そうした人々は)別の考えを持つ人と境界を作り、分断が起こっている。―
もう一つは、3.11後に「3がつ11にちをわすれないためにセンター(通称:わすれン!)」を立ち上げ活動を続けている、せんだい・メディ アテークの甲斐賢治さんのお話から。。。
― 「震災以降とにかくいろいろなところに〈隔たり〉が生じているように感じられました。被災直後すでに、これらの〈隔たり〉によって、さまざまな問題が出てくるだろうと予想されました。そうやって、他者との距離が生じると、語れなくなり自閉していくだろうと。そうであるならば、その〈隔たり〉を行き来する「回路」をつくることが生涯学習施設の活動テーマになるのではないかと考えました。ビデオカメラを持って海岸部に行くことも、知人同士でインタビューし合うことも他者を知る回路となり得る。「あの時のことを語りなおすこと」は「隔たりの向こう側を想像すること」となり、他者と自分とを照らし合わせ、それが結果自身を落ち着かせ、あらためて考えていくことにもつながるのではないか」―
そしてもう一つは、先般プリツカー賞を受賞された建築家・山本理顕氏のお話から。先ごろ、残念ながら逝去された東京大学名誉教授・建築家・原広司先生のもとで世界各地の集落調査に携わられてきた山本さんは、集落調査から学んだこととして、
― 経済単位としての村やそのまちなみは個性的で美しい造形力を持ち、過去の記憶とこの場所に住み続ける意思を伝達する装置として、建築物はその重要な役割を果たす。家の外と中をつなぐ空間としての「閾(しきい)」の存在が、住人の意識を内に向かわせコミュニティーを拒絶するようになった現代の建築では損なわれている。かまち、縁側、閾といった、家の外と中とをつなぐ中間的な空間が、地域社会圏を創り続けるために必要、と。―
Living Together… みんな一緒だから、いろいろな人たちが集うことで境界が曖昧になり、壁や境目を超えてゆけるから。だから楽しい。そんなことを問いかけ続けてゆけるような取組についてを、きっと、最前列の高校生のみなさんが、これから、五感全てを使って、他者とのかかわりあいのなかで、Co-Becomingしていかれるんだと、そう信じています。
そして、島国根性、関係人口、限界集落… それらは、私たちが自分たちでつくってきた〈隔たり〉。その向こう側を想像すること、を、続けられるかどうか、の問い直しをしていくということであるのかもしれません。10回の軌跡、奇跡のなかで「隔たりを行き来する回路」を、特別授業に参加してきてくれた、特に高校生の皆さんが自分の中で作り、はぐくんでいることに確かにつながっている、とそう信じることができた初夏のいちにちに、心からの感謝です。
― 閉鎖性、排他性を本質的にもつ同質社会の幻想に強くひたり、巨大な車座を組んでいるともいえるこの国において、同心の者たちは心を合わせて互いの健康と繫栄を謳歌し、車座を組んで互いの顔を見合わせながら志気を高揚させ、鼓舞しあう。しかし彼らは、車座の輪の外側にはほとんど関心を払わない。純真に心を合わせることは、異見をもつ者、孤心を磨く者に対する排除と一対である場合が多い。―
大岡信『うたげと孤心』より。
車座の輪の外側に関心を持てるように… と、この取り組みを進めてきた人たち、支えてきた人たちは、異見をもつ者、と出会うことを歓待しようとし、そうした場でありたいと希ってきたんだ… 特別授業は年に1回ですが、この間それぞれのスキルを出し合って、この稀有な取組に集ってきたみんなが… 第11回目、きっとある、と希いつつ。